本当に透明感のある演技で、実在していたかのような錯覚をおこされる演技です。松たか子は、ズバぬけて美人という訳でもないけど見ているうちにどんどんその姿や顔がきれいに見えてくる女優さんで気品があるので、時代物も難なくこなしてしまいます。なんとなくこれを見て、大河ドラマ主演を見てみたい!!と思ってしまいました。NHKは本当にドラマを丁寧に作っていて役者にも妥協がなくて安心感がありますよね。タイトルの「櫂」の意味は全編を通して、女性が自分の足で立って自分で生きていくという事を示しているのですがすばらしかったです。宮尾登美子原作で松たか子のドラマのシリーズをもっと見てみたいです! 関連情報
この回では、やはり義高暫首を決定する頼朝の孤独な苦悩ぶりがから、目を離せません。北条政子の『頼朝さまは、普段は義高暫首後の娘大姫の嘆きぶりにうろたえる姿を見ても分かる通り情のお人なのに、その情の心に蓋をして理という鎧を二重にも三重にも身につけている』というセリフからも頼朝の一言では形づくることの出来ない人物像を本当に良く中井貴一さんは演じ分けていると思います。また、義経に語ったセリフで『新しい世というのは、何も源氏の世という訳ではない』『一族でなければ結束出来ないというわけではない』『自分が目指すのは、新しき武士の世じゃ』という言葉がとても印象的で説得力があり、しかも、義経が一の谷で生け捕りにした平家方の重ひらと昔話をするシーンも、情緒あふれ、物悲しく切ない運命をかんじ、屋島では、佐藤継信が討死してしまったり、梶原景時と逆櫓問題での言い争いなど名場面が、盛り沢山です。 義経 完全版 第五巻 [DVD] 関連情報
宮尾登美子の『綾子』物語は多数あるけれど、まずはこの作品から読むことをおすすめしたいです。綾子満6歳から、高女を出て臨時教員になり未来の夫に出会うまでを書いています。それでも読むことを続けてしまう文章力があり、まずこの作品を読んで、母・喜和の『櫂』を。綾子苦難の『朱夏』、帰国後を描いた『仁淀川』、そして父・岩五の『覚書き』と読んでいくとだんだん綾子を好きになっていく自分がいました。 春燈 (新潮文庫) 関連情報
満州における敗戦前後、530日余の凝集された出来事を本書にたどると多くのことが脳裏に去来する。満州での日本人の生活はどんなだったか 敗戦前後でどう変わったか?人間は、過酷な境遇にどう耐えたか、耐えられなかったか?人間は、植民者としての行動や極限状況の行動をどのように意義付けて平安に生き続けようとしたか?地位、職業、欲望とはそれぞれ何か?植民者としての民衆は、植民地でどう行動したか?中国人は終戦を挟んでどう行動したか?そして、結局、満州とは何だったのか?答の一部は事実描写と主人公綾子の考えと取り巻く人々の言動で示され、いくつかは暗示でとどめられる。著者の経験に基づく、迫真のリアリズムである。子の世代が親の世代より前進するには、親爺の背中やおふくろの味、親たちの成功と失敗など、親たちの世代と向き合ってそれを超えようとするのがもっとも確実な道ではなかろうか。現代の若者たちが、父母や祖父母の世代のことをしっかり理解し継承することは、これからの時代をより良いものにするためにとても大切なことだと思う。宮尾さんは、そのような理解を得る格好の事実を自らの経験の中から紡ぎ出して文学に結晶させてくれた。 朱夏 (新潮文庫) 関連情報
この小説は、言うまでもなく著者・宮尾登美子の自伝小説である。土佐で生まれ育った宮尾が、一見華やかな花柳界の裏側や、生き地獄のような貧民窟の様子を、ありのままに描いている。それはもう想像を絶する世界で、こういう特殊な環境にいた人でなければここまで詳細を語るのは難しいだろう。時代は大正から昭和戦前までのことだが、ここに登場する貧民窟は、何も高知のこの場所に限定してあったわけじゃないだろう。おそらく貧しい日本の各地に存在したに違いない。長い棟割長屋に住む子どもたちは皆、覇気がなく、虱だらけの頭でボサボサにし、猿股も腰巻も着けていないのに何の恥じらいもない。老婆は出入口の傍にある便壺に、他人の目も気にせず小水の音を立てる。よそ者が一歩間違えてその地域に迷い込んでしまったら、一面に漂う悪臭に一分と我慢できないところなのだ。一方、華やかな花柳界を牛耳る元締めは、抱えの娼妓が妊娠しても臨月まで客を取らせ、流産しても商売を休ませないという血も涙もない労働体系を取っている。それはもう生き地獄のような世界なのだ。人は皆、多かれ少なかれ苦悩を抱えて生きている。だが、現代を生きる我々は、憲法によって基本的人権の尊重が保障されている。なんとありがたいことか! 同じ人間、同じ日本人でありながら、わずかに生きる時代が違うことで、極貧に喘ぎ、人としての存在価値すら危ぶまれる境遇に身を落とさねばならなかったかもしれないのだ。今は本当に女性の立場が強くなった。以前は考えられなかった男性の領域にもどんどん進出し、女性には対等な職種も与えられるようになった。女性はその性差によって、生まれながらにして男性の下に置かれ、嫁いでは夫に仕え、老いては子(長男)に仕えた。三度の食事も温かいご飯にはありつけず、夫と夫の親、そして子どもらが済ませてから漸く冷や飯をかきこむのが日常だった。そんな性差を小説の内側から垣間見てしまうと、なんともやりきれない気持ちでいっぱいになる。『櫂』は、決してジェンダー論を問う小説ではない。ただ事実を淡々と、そしてドラマチックに追うものだ。そこに鮮やかに浮かび上がる高知の下町の光景や風物が、現代を生きる我々の胸に揺さぶりをかける。必死に生き抜く女たちの哀切極まりない嘆きが聞こえてくる。読後は、口先と暴力に頼む男たちの虚しい性に、改めて人の業を見たような気になる。大正〜昭和戦前期を知る作品だ。 櫂 (新潮文庫) 関連情報

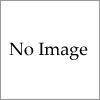
![義経 完全版 第五巻 [DVD] 宮尾登美子](http://ecx.images-amazon.com/images/I/2161Y6Q9THL._SL160_.jpg)

























![[ミズノ] MIZUNO サッカーシューズ MONARCIDA FS AS [ミズノ] MIZUNO サッカーシューズ MONARCIDA FS AS](http://images-jp.amazon.com/images/P/B00S0HZBVS.09.MZZZZZZZ.jpg)


