
スピリット・オブ・ヒーリング~バリ
サウンドスケープ系、ヒーリング系ですが、鑑賞用に充分耐えうる作品。
シンプルで雰囲気たっぷり、これほどバリの空気感が出たCDは他にないのでは?
この手のアンビ・バリ系では最高の作品です。ヨガやエステのBGMとしても大OKでしょう。
シンプルで雰囲気たっぷり、これほどバリの空気感が出たCDは他にないのでは?
この手のアンビ・バリ系では最高の作品です。ヨガやエステのBGMとしても大OKでしょう。

Otome continue Vol.1
コンティニューが、オトメコンティニューとリニューアルされての創刊号。
特集内容は、『ときめもガールズサイド』!!
当初は、リニューアルはこれまでの題材の取り上げ方で視点を変える(オトメ向けというか、オトメ寄りにする)のかな?と思っていたけど、その間逆で視点は変わらず題材がオトメ向けド直球になったな、という感じ。
勿論、巻をかさねていくなかでさらなる変貌を遂げるかもしれないけど、変化についていけない部分も感じた。
購入を躊躇う思いにつながる感じで・・・。
でも、『ときめもGS』特集中の、声優・杉田智和さんが、「女性向けだからといって、男性が手を出しちゃいけないというわけではないと思う」という発言に心情をダブらせ購入に至りました。
サブ特集の、相方語りでオール巨人・阪神が出てきて、「あぁ、読んでいけそうだ!」と思った。
内容のレベルとしては、今まで通り面白い視点に溢れていて凄く楽しめた。
ただ、やはり男性向け・女性向けで区別するとしたら女性向けに特化されたのは間違いないので、リニューアル前の読者が多少離れるかも、と思った。
特集内容は、『ときめもガールズサイド』!!
当初は、リニューアルはこれまでの題材の取り上げ方で視点を変える(オトメ向けというか、オトメ寄りにする)のかな?と思っていたけど、その間逆で視点は変わらず題材がオトメ向けド直球になったな、という感じ。
勿論、巻をかさねていくなかでさらなる変貌を遂げるかもしれないけど、変化についていけない部分も感じた。
購入を躊躇う思いにつながる感じで・・・。
でも、『ときめもGS』特集中の、声優・杉田智和さんが、「女性向けだからといって、男性が手を出しちゃいけないというわけではないと思う」という発言に心情をダブらせ購入に至りました。
サブ特集の、相方語りでオール巨人・阪神が出てきて、「あぁ、読んでいけそうだ!」と思った。
内容のレベルとしては、今まで通り面白い視点に溢れていて凄く楽しめた。
ただ、やはり男性向け・女性向けで区別するとしたら女性向けに特化されたのは間違いないので、リニューアル前の読者が多少離れるかも、と思った。

サンセット・ギャング
リアルタイムで聞いたこの音30センチLP盤から流れ出た懐かしい音にくすぐられました。
今聞いても何も古くなく、私の子供たちにとってはとても新鮮に聞こえているようです。
このゴジラにもう一暴れしてほしいものです。
今聞いても何も古くなく、私の子供たちにとってはとても新鮮に聞こえているようです。
このゴジラにもう一暴れしてほしいものです。

世界の音を訪ねる―音の錬金術師の旅日記 (岩波新書)
ワールド・ミュージック界の仕掛け人が、最近流行のブラジル北東部(ノルデスチ)の音楽や、モロッコのグナワ音楽を追い、現地を訪ねて音楽と触れ合う、非欧米圏の音楽好きにはたまらない上質の音楽ルポだ。また所々に散りばめられた直感的な指摘もなかなか鋭い。例えば、インドネシア・スンダ地方(ジャワ島西部)のポップ・スンダと日本の歌謡曲のメロディが類似しているのは、日本統治時代に双方の音楽関係者が交流したからではないかとか、関西弁が抑揚の変化に富んでいるのは、古代より渡来人が多く、彼らの唄うような四声を粋に感じた人々が、一種のシノワズリとしてその抑揚をまねたためではないかとの指摘には、なるほどと思った。ちなみに後者の意見は、小泉保『縄文語の発見』に似た論旨で書かれていました。


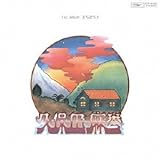



![君が想い出になる前に[네가 추억이 되기전에] - Yukie Nishimura(西村 由紀江)_Instrumental 君が想い出になる前に](http://img.youtube.com/vi/Zmp8EG6mQRU/2.jpg)

