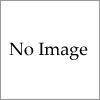
テヘラン商売往来―イラン商人の世界 (アジアを見る眼)
イランの繊維業界のフィールド・ワーク経験から、筆者がであったイラン商人たちの像を親しみやすく描き出しています。
読みすすめるうちに、次々と出てくるペルシャ語の商売にまつわる用語にとまどうするかもしれません。
しかし、身近な日本の商売にあてはまるものを思い出しながら読めば、分りやすく読めるでしょう。
世界のどこに行っても、商売に大切なのは人とのつながりや、情報力/判断力などのスキルがたいせつで、基本的な
ことは変わらない、ということが実感できると思います。
この本のベースとなっているのは、筆者の10年にわたる取材経験ですが、「あとがき」には、イランの地にも
グローバリゼーションの波が押し寄せている事を示唆しています。
この本のその後についても、続編というかたちで書かれることを期待します。

テヘランでロリータを読む
アメリカのベストセラー。2006年末にいろいろな書評で絶賛されていたので(若島正、巽孝之、小池昌代、、、)読んでみた。
ホメイニ革命が起こった後、イランでは自由に小説を読むことも難しくなり、どのような作品も、イスラムの教理にあわせて教条的に読むことを求められることになった。ジェイ・ギャッツビーは堕落した文明が生み出したろくでなしである、とか、デイジー・ミラーは男をみだりに誘惑する悪魔である、とかね。そういう空気に侵されたテヘラン大学で英米文学を教えるナフィーシーさんは、そういう風潮に反発を覚えて自由に小説を読むための読書会を毎週ひらくようになる。そこで、『ロリータ』、『グレート・ギャッツビー』、『デイジー・ミラー』、『高慢と偏見』なんかを読んで、みんなであれやこれや話をする。「やっぱり文学っていいよね」って。そりゃそのとおりで、イスラム教的な解釈を強制されながらギャッツビーを読むくらいなら、交通標語でも朗読してた方がよっぽどましである。解釈を強制されるとのはある意味楽ちんなんだけどね。日本人でも「国語は決まった答えがないから嫌いだった」というような人もいると思うし。しかし、文学テキストを解釈するという訓練は、答えがないことに耐える訓練でもある。そして、その忍耐力は、実は世の中では大変実用的なのである。
さて。
と、いうことで、文学の力強さのようなものを描いているということで、文学関係者には評判がいいのだな、と合点がいった。また、舞台がイランだから、アメリカ人は「やっぱりイスラム原理主義ってだめよね」っていう感じでおもしろく読むのだろうね。しかし日本人の一般読者向けにはアピールがちと弱い気はする。
あんまり関係ないけど、アメリカでこの間イラン人と仕事をした。とても合理的で素晴らしいビジネスマンだったよ。



![Radio2.4km@youtube No.78 review vol.3 [ 十二人の怒れる男 ] 十二人の怒れる男](http://img.youtube.com/vi/IuDK3_7Sx0o/3.jpg)
![[本編]part 1 /6 映画「福井青春物語」2005 津田寛治](http://img.youtube.com/vi/dCPxOZP4BOo/1.jpg)


