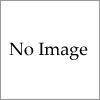
私はイヴ―ある多重人格者の自伝 (ハヤカワ文庫NF)
本書は治療を担当した医師の手による著作「私という他人」を訂正するつもりで患者本人が書いた自伝である。「私−」を読んでから本書を手に取った人は私同様驚くだろう。その違いは「私−」というタイトルが悪趣味な洒落なのかと思ってしまうぐらいだ。治療にあたった医師たちはプライドにかけて治癒したことを宣言したかったのだろうが、実際には本人の症状と苦しみの事実が医者には正確に伝わらず、患者やその家族がいかに苦難の人生を歩んだかと言うことが分かる。
「ビリー・ミリガン」「シビル」「イヴ」、一連の本に言えることだが、分裂した人格間の比較や人格統合の経緯も非常に面白いのだが、人格が分裂する背景や経緯をもう少し病理学的に解説して欲しかったと思う。幼少期の虐待の影響や、なぜアメリカに症例が多いのかなど興味があるところだ。

イブの三つの顔 [DVD]
事実は小説よりも奇なり、と言いますが、それは当たり前の話で、小説(フィクションの意味で)だからこそ、万人を納得させられるだけのプロセスや説得力がないと受け入れられないものです。
だから、事実を元にした小説や映画は、モデルがあるという背景を知らないと、荒唐無稽なだけで、なかなか受け入れられるものではないでしょう。
この作品は多重人格という稀有な症例を扱っているだけに、そういう意味では難しいテーマであり、それゆえに監督の力量や女優さんの演技力に追う部分が大きいのではないでしょうか。
主演のジョアン・ウッドワードの熱演には惹きつけられますが、やはり見ていると時代を感じる部分もあります。1957年の公開ですが、はすっ葉なキャラクターを演じる時にもどことなく上品で、女優としての矜持を崩していません。これをもし、現代の俳優が演じたらどうなっただろうか、と何となく興味もあります。
この多重人格に関しては、唐突ではあるものの、個人的には意外に不自然さは感じませんでした。
当人に記憶が欠落しているという点は異常かもしれませんが、抑制が大きいとこのモデルのケースのように変わった出方をするのではないか、と勝手に考えます。一番の問題は、このイブのケースのように社会的話題になったり、高名な医師の研究材料になったことではないか、という皮肉な解釈をしてしまいます。
平凡な主婦の秘めた人格、というといかにも特別な症例のように見えますが、この複数の相反するキャラクターは誰でも持っている側面で、特に女性にはみんな、外に見せない秘めた内面があるような気がします。
そもそも、平凡で貞淑な主婦、という人格じたい、とってつけたような観念的なもので、誰もがみんな、どこかトンがった部分や毒を持っているもので、ほんとに絵に描いたような平凡で貞淑な女性が存在したら、そっちのほうが不気味です。
現代では、それを自分で意識して毒を解消したり、或いは芸術や仕事の上で昇華するという手段がありますが、この時代背景だと、女性はこうあるべきだ、という意識が強く、ましてアメリカの田舎の閉鎖社会、変にこもって捻じ曲がった表現になったという解釈もできます。
そういう意味では、ジョアン・ウッドワードの演技も、時代の意識の範疇でしか淫らな女を演じてはおらず、この映画じたいがこの症例を産み出した時代の産物という考え方もできます。
女性の怖い裏面を垣間見たことのある人間として、勝手な解釈をしてみました。。。






