
暗殺者の森 (100周年書き下ろし)
初めてこういう手の小説を読みました。
これがシリーズものとは知らなかった。
世は第二次世界大戦も終盤へとさしかかった頃です。
重要な登場人物たちの性格が出ていて
ほどよく緊張感もあり、それでも戦争という舞台に
物語が濃くなりすぎる事もなく読みやすかったです。
とくに物語の終盤にさしかかり、
ヴァジニアと北都がどうなるのかも
ワクワクさせられました。

暗殺の森 Blu-ray
ベルナルド・ベルトルッチとヴィットリオ・ストラーロのコンビが生んだ至高に美しい作品です。ワンカット、ワンカットが芸術写真のようでうっとりしてしまいます。光と影をこれほどまでに映画の雰囲気に合わせてコントロールできた監督と、撮影監督は彼らしかしかいないのではないかと思わせる程、すばらしい!映画ファンのみならず、写真や映像、美術、衣装、ヘアメイク、照明などに興味がある人には必見の作品です。とにかくレベルが違います。本物とはこういう物なんだと、目から鱗が落ちること間違いありません。
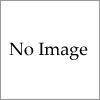
暗殺の森 完全版【ワイド版】 [DVD]
高い評価のレビューが多いこと、映像美の作品であるらしいこと、個人的に気になる俳優さんが出演していること、で購入。
はたして映画ド素人、かつ歴史に疎い私に、理解できるのか?・・・と不安はあったが、映像はド素人が見ても鳥肌が立つほど美しかった。まるで動く絵画。ローマやパリの外観も内装も趣のある建物。出演者の個性的な美を際立たせる衣装。光と影。
美しすぎる映像と、政治的思想が絡むストーリーに、ド素人は身構えてしまうのだけれど、実は物語は普遍的で、「正常な」人生を求める青年が、時代に翻弄されてしまうのだった。
美しい映像は、ロケーション撮影が多い割に狭くもあった。一因は人工物の多さかもしれない。きちんと整備された都市。懺悔するための小部屋や電車のコンパートメント。広い室内はわざわざ区切られたりして、なんだか狭い。屋外でも、何らかの「格子」が画面の上から下まで貫いていたりするので、マルチェロは檻の中にいるかのよう。暗殺が行われる森でさえ、針葉樹らしい長い幹は空まで続く広大な牢獄のよう。
物語中、この牢獄の「外部」にいるのは、吠える犬や、音楽を奏でる浮浪者くらい。一方、いくつかの室内は不必要なまでに広く、マルチェロの父親が入院する精神病院など無限に広く見えて不安感を煽る。
マルチェロが「正常」でありたいと強く願うようになったきっかけは、幼い頃ホモセクシャルの運転手リーノに悪戯されかけ殺してしまった思い出である・・・という解説が付属の小冊子にあったが、私にはその前の「いじめ行為」が真のきっかけに見えた。
だけど幼い少年は、「集団で取り囲んで服を脱がす」行為を「異常」だとは思わずに、そんな目に遭う「自分」をこそ「異常」だと思うらしい。リーノを糾弾し、彼を殺した自分を懺悔するマルチェロ、集団を糾弾したり、集団に懺悔を求めることは、しない。
この場面、少年がリーノの「長い髪」と「銃」に触れるのが印象的。リーノの「女性性」と「男性性」。
『昼顔』でもそうだったが、なんでこういう「揺れ動く」役柄が似合うんだろう、ピエール・クレマンティ。
美しすぎる牢獄をつくったのは「群衆」に怯えるマルチェロ自身。
彼が恐怖するのは、「群衆」特有の、「個」を失った、まるで植物のような「大きな意志」。
・・・と(勝手に)仮定してみると、無教養かつ俗物であると見下していた新妻ジュリアが、ダンスホールで堂々と女性同士で踊り、あまつさえ「群衆」を先導し外に飛び出していくシーンは、かなり面白い。内側に留まり困惑するマルチェロ、渦のような「群衆」に囲まれて身動きがとれない。なぜ妻は受け入れられ、自分は排除されるのかが、彼には理解できないのだ。
「群衆」は「個」になるや、やおら異常性を見せるのも面白い。マルチェロの両親、同志、反ファシズムのクアドリ夫妻、みんなどこかおかしい。「正常である」ことが「多数派である」ことなら、マルチェロはあまりに「正常」すぎるからこそ「異常」って、なんだか皮肉な世界観。
当然のことながら、撮影するカメラも、牢獄の「外部」に存在していて、優れた映画を創造する才能も一種の「異常」な行為、もちろんそれを喜んで観ている観客たちも・・・と考えてみると、「正常」なマルチェロは、ほんとうに孤独なのだった。
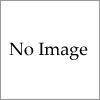
暗殺の森 完全版【字幕版】 [VHS]
モラヴィア×ベルトルッチという20世紀のイタリアを代表する作家と映画監督の夢のようなコラボレーション。
アルベルト・モラヴィアの作品は『倦怠』『深層生活』『金曜日の別荘』など様々な監督が映画化していますが、性を磁場にした退廃性のせいかポルノグラフィー的な解釈をされたものも多く、唯一原作の品格を損なわずに最高の状態で映画化されたと思うのがこの『暗殺の森』です。
流麗なカメラワークにドラマチックでありながら行き過ぎない演出、素晴らしいセットと衣装、そしてフランスを代表する映画音楽家ジョルジュ・ドルリューによるオリジナルスコア・・・一切が手抜きなく、ヨーロッパらしい映像芸術の醍醐味を感じさせてくれます。
好対照な魅力で光を放つドミニク・サンダとステファニア・サンドレッリという華やかな女優陣に対し、内省的でインテリジェントなイメージのジャン・ルイ・トラティニアンという配役もいいですね。性倒錯者の役でちらっと顔を出すフランスの個性派俳優ピエール・クレマンティ(『昼顔』『豚小屋』etc.)も素敵!
有名なタンゴのシーンの他どこをとってもフォトジェニックで、古いモード雑誌でも眺めるようなお洒落さも感じます。
ファシスト政権に弾圧を受けた作家が書いたイタリアの現代史ともダブるストーリーですが、たとえ政治色の強いストーリーに共感できなくとも、映像だけでも十分に楽しめるところは監督の優れた手腕じゃないでしょうか。
ベルトルッチは『ラストエンペラー』あたりから個性に乏しくグローバル化し、残念ながら私にはもはや興味のない監督になってしまいましたが、'70年代頃の様式的で耽美で感傷的な作品の数々は彼らしくて大好きです。感情表現の激しさと豊かさはラテンの気質ならでは。ファッションやデコレーションに対する美意識の高さもイタリア人らしいと思います。







